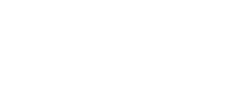第2941号 令和7年11月16日
今後の事業日程等を確認
新年賀詞交歓会に関し意見交換
岐阜県管工機材商組合 2025年10月度理事会開催
岐阜県管工機材商組合(理事長=森浩氏・山兼社長)は10月16日午後5時より、岐阜市柳ケ瀬通(通称・西柳ヶ瀬エリア)にあるホテルグランヴェール岐山にて10月度理事会を開催した。同日午後4時からは同ホテルにて全員例会「ポンプ講習」(若手営業育成支援)も開催されている。
理事会には理事8名が参加。森理事長が「先ほどは全員例会でポンプの講習を行いました。皆さま方のお役に立てたのではと思います。ポンプというものは触らないと分からないもので、講習を聴いたからといってすべてが分かるわけではありませんが、今日聴いていただいた基礎的なことだけでも覚えていただければと思います」と、全員例会の感想を交えて挨拶した後、さっそく以下の議題についての審議・報告へと移った。
【議題1】親睦ゴルフ開催について▽開催日時は11月6日(木)、開催会場は岐阜関カントリー倶楽部 西コース(岐阜県関市山田芳洞/本紙発刊時、開催済み)。理事会当日現在、正会員・賛助会員合わせて26名が参加申し込みしている。
【議題2】全員例会について▽本理事会開催前の午後4時より、同じくホテルグランヴェール岐山で「ポンプ講習会」を開催。参加人数は22名。講師は、テラル多久の塚原英之氏、テラル岐阜営業所の大橋功所長が務めた。主催は同組合実務責任者会議「木曜会」だ。
【議題3】2026年新年賀詞交歓会について▽開催日時は2026年1月29日(木)午後6時(受付開始は午後5時40分)より、ホテルグランヴェール岐山での開催が決定した。本理事会では、各理事の当日の役割分担の確認のほか、前年の反省を踏まえて、来賓控室やクロークの準備、周辺駐車場の告知の徹底、来場者への手土産の選定などについて意見を交換し合った。
以上、すべての議題審議が終了し、本理事会は閉会となった。次回は12月4日(木)午後6時より、ホテルグランヴェール岐山にて、忘年会を兼ねた理事会の開催が予定されている。
木曜会主催の若手営業育成支援
「ポンプの基礎」学ぶ講習会開催
岐阜県管工機材商組合は10月16日、理事会に先立つこと1時間前の午後4時より、ホテルグランヴェール岐山にて、正会員企業若手営業員育成支援の一環として全員例会『ポンプ講習会』を開催した。主催は同組合実務責任者会議「木曜会」。講師はテラル多久(所在地=佐賀県多久市)製造部営業サービスグループの塚原英之氏と、テラル中部支店岐阜営業所(所在地=岐阜市六条南)の大橋功所長が務めた。正会員企業の経営者や実務責任者など、合わせて22名が参加し、ポンプの基礎を学んだ。
森理事長が冒頭「今日は全員例会として、ポンプの基礎を皆さんと共に学ぶ時間を設けさせていただきました。本日の講師は、テラルグループのテラル多久株式会社さまにお願いしました。テラル多久さまは佐賀県多久市にある企業さまで、2003年にテラルグループの一員となり、2008年に現在のテラル多久と社名変更されました。本日はわざわざ九州からお越しいただきましたので、短い時間ではございますが知識を吸収していただいて、社業に役立てていただきたいと思います」と挨拶した後、講習会が始まった。
この日のテーマは「ポンプ・送風機の基礎」。建築市場におけるポンプ・送風機の用途に始まり、具体的には住宅・非住宅別でどんなところに使われているのか? これらの役割や種類、また、原理・構造、使用箇所別の選別方法など、約1時間と限られた短い時間ではあったが、ポンプ実機を実際に間近で見学しながら、しっかりと基礎内容が参加者にレクチャーされた。
2025年9月の工作機械受注総額
前年同月比11%増の1391億円
日工会 「受注は緩やかに展開」
日本工作機械工業会(日工会、会長=坂元繁友氏・芝浦機械社長)が10月21日発表した2025年9月の工作機械受注額(確報値)は、総額が前年同月比11・0%増の1391億46百万円で、3か月連続して前年を上回った。
内需は、前年同月比5・1%増の436億45百万円。年度上期末の効果により6か月ぶりの400億円超えとなったが、直近5年間の平均と比べやや低い水準。
主要業種では「航空・造船・輸送用機械」が前年同月比3倍強の64億円と過去最高額を記録した一方、「一般機械」「自動車」「電気・精密」は減少した。
外需は、前年同月比13・9%増の955億1百万円で、12か月連続の持続的な増加を示した。
主要3極では「北米」が19・3%増の295億円、「アジア」が15・9%増の496億円、「欧州」が15・1%増の155億円だった。
同工業会は受注の先行きについて「米国の関税措置が一段落するも、国際情勢の明るさは見通せない中、慎重な動きが見込まれる。概して堅調ながら第4四半期の回復に期待」するとしている。
会員企業社員35名が参加し
給水装置に使用される自動弁を学ぶ
中部桃友会 第37回社員技術研修会開催
中部桃友会(会長=大藪淳一氏・大清社長、ベンと販売店の会)は10月14日、名古屋市中村区の安保ホールで『第37回 中部桃友会 社員技術研修会』を開催。会員企業の社員35名が参加し、座学と実習で「弁」の基礎知識を学び、体感した。翌15日には、静岡地区の中部桃友会会員企業社員を対象とした研修会が開かれている。
開会に先立ち、大藪会長が「本日は35名と大変多くの方にご参加いただいたうえ、女性の方の参加も多く、本当にありがとうございました。ベンさんは1950年にフシマンバルブ製作所として岩手で創立され、今年で75周年を迎えた歴史あるメーカーです。近年では岩手と相模原両工場をリニューアルされ、2023年には横浜の関内に自社ビルを購入されて本社を移転するなど、自動弁のトップメーカーとしてますます発展されています。この中部桃友会ですが、ベンさんの商品を取り扱う販売店の会として、会員企業全社でベンさんの商品を拡販していこうという集りでございます。今日は座学はもちろん、この研修会の特徴である、手に取って分解・組立まで行う実習も体験していただきます。こうして得た知識を自社に持ち帰って、さらなるベンさんの拡販につなげていただければと思います」と参加者に挨拶。その後、第一部の座学が始まった。
座学では「給水装置に使用される自動弁」について、給水方式の違い、給水装置に使用される減圧弁や水撃防止器、空気抜弁、機械式緊急遮断弁などの用途や構造、作動の仕組みなどを学んだ。
実習では、参加者は3つの班に分かれ、各班順番に「分解・組立」(空気抜弁・吸排気弁・定水位弁・逆止弁)、「作動実演」(空気抜弁・吸排気弁・減圧弁・定水位弁など)、「ベン新商品・販売強化商品の紹介」(カートリッジ式減圧弁RD-56N型、カートリッジ式戸別給水用減圧弁RD-57N型、スチームトラップAF-23/23F型、液体用遮断弁MR-7CRN型など)の各セクションを回り、本物の弁を手に取り体感した。
現在ベンは、外部動力不要の震災対策用機械式緊急遮断弁(EIM型シリーズ)を販売強化商品と位置付けている。また8月には、フロート式スチームトラップ(AF-23型/23F型)、カートリッジ式戸別給水用減圧弁(RD-57N型)を連続して発売。年末に向けてもまだまだ新商品の発売が控えているという。
バルブ業界の現状について聞く
物流問題に関する協議継続
静岡県管工機材商組合 2025年度10月理事会を開催
静岡県管工機材商組合(理事長=丸尾高史氏・丸尾興商社長)は、10月16日午後3時よりGRILL炙之介(静岡市葵区)において10月理事会を開催した。理事ら11人が出席した。
議事に入る前に、バルブ機工部会(担当理事=和久田利光氏・浜松管材会長)が開かれ、講師を務めたキッツ東海営業所の黒川所長が「バルブ業界の現状」を説明。品種別生産実績や品種別トン当たり金額、最近10年間の需要部門別生産・出荷額実績を示すとともに、キッツが取り組む重点市場別製品戦略について説明した。また、IoT・AI技術を活用して遠隔でバルブの状態診断及び故障の予兆検知をするバルブ監視システム「KISMOS」の紹介では、導入にあたっての質疑応答などが活発に行われた。
続いて、理事会の各議題について報告及び審議が行われた。
物流問題進捗報告では、丸尾理事長より、組合で作成した文書に対する同社顧問弁護士の見解と対策が報告された。引き続き協議を継続していく。
10月28日の管機商ゴルフ大会について、伊藤りゅういち副理事長(ヌマカン社長)より、日時、会費、ルール、組み合わせ等の説明があった。11組44人の参加で開催予定。服装(寒さ対策など)への注意も促された。当日は事務局も運営の手伝いをする。また、12月3日の理事会忘年会/ゴルフ会の説明があった。
9月9日に開催したボウリング大会の報告が、村松商店倉嶋常務(村松美和副理事長代行)より行われた。36社67人(男性65人/女性2人、正会員19人/賛助会員48人)の参加で無事終了。こういう企画を待っていたとの声もあり、次回開催(来年)も検討する。若手や女性の参加を増やしたいとし、女性に対してハンデ(30点が妥当か)を付ける。
次回理事会は、11月11日午後3時よりGRILL炙之介にて開催する予定。
計測・加工・制御に関する
研究者22人と2団体に助成金
三豊科学技術振興協会 ミツトヨ本社で交付式
公益財団法人三豊科学技術振興協会(理事長=水谷隆氏、所在地=川崎市高津区)は9月24日、計測・加工・制御に関する研究を対象とした2025年度の研究助成、国際交流「渡航」助成で助成する22人の研究者と、国際交流「会議」助成で助成する2団体を決定したと発表した。10月25日には川崎市のミツトヨ本社において、研究助成の10人に対する交付式を行うとした。
今回の助成総額は2384万円。内訳は、研究助成が10件で2000万円、国際交流助成は「渡航」助成(第1期6件、第2期6件)および「会議」助成(2件)で384万円となった。
同財団は精密測定機メーカーのミツトヨと元代表理事・故沼田智秀氏をはじめとする5人の出捐により1999年に設立され、これまでの27年間に計581件、6億8168万円を助成してきた。
本年の研究助成対象者とテーマは次の通り。(敬称略)
江川悟(東京大)「2次元湾曲結晶による単色X線ナノプローブの開発」▽金子和暉(岡山大)「研削加工の作業条件最適化のための包括的シミュレーションの構築」▽楠山純平(千葉工大)「次世代半導体ウェハのロータリ研削において加工条件が内部ひずみにおよぼす影響」▽桑原央明(芝浦工大)「全身力覚推定機能を有する車椅子の開発と搭乗者姿勢制御の実現」▽佐藤遼(東北大)「超精密ステージ角度運動誤差計測用の学習型推定モデルに基づく広範囲作動距離3軸角度センサの開発」▽清水祐公子(産総研)「精密測長のためのテラヘルツ分光を用いた非接触・高精度な空気の熱力学温度計測技術の開発」▽孫栄硯(大阪大)「大気圧プラズマジェットによるSiCミラーのナノ精度形状創成プロセスの開発」▽藤大雪(大阪大)「光電気化学酸化を利用したGaN成長用種基板表面の高精度平滑化技術の開発」▽水上孝一(東京都立大)「アコースティックエミッション信号の選択的増幅のための3DプリントABH導波構造の開発」▽山口桂司(京都工繊大)「レーザースペックル法を応用したインライン砥石作業面診断システムに関する基礎検討」
以上10件
売上高・利益ともに過去最高
岡谷鋼機 令和8年2月期中間決算
岡谷鋼機(社長=岡谷健広氏、本社=名古屋市中区)は9月30日、名古屋証券取引所において令和8年2月期中間連結決算の説明会を開催した。
決算は、売上高が5706億円(前期比5・7%増)と2期ぶりの増収。利益面では営業利益が213億円(同23・6%増)、経常利益が244億円(同28・4%増)、親会社株主に帰属する中間純利益が162億円(同31・2%増)といずれも5期連続の増益で、売上高・利益ともに過去最高となった。
セグメント別では、情報・電機セグメントが情報インフラや自動車関連の増加により17・2%の増収。生活産業セグメントは昨年8月に設立した配管機器事業会社が加わった影響等で39・2%の増収と大きく伸長、産業資材セグメントも4・6%の増収となった。一方、鉄鋼セグメントは建材関連及び原料、欧米・中国向けなどの減少により6・8%の減収となった。
中間期末の連結関係会社数は前期比2社増の100社(国内48社、海外52社)となっている。
通期の連結業績予想は期初予想を据え置き、売上高1兆1000億円、営業利益340億円、経常利益380億円、親会社株主に帰属する当期純利益250億円を見込む。
岡谷社長は下期の見通しについて「関税問題はようやく税率が決まり、これから各企業の動きが出てくる。サプライチェーンの変更や材料調達先の見直しなどがあると思われ、まだ不透明要素は残る」とし、情報網を駆使して迅速に対応していく考えを示した。
また、自動運転システムの開発を行うマップフォー(社長=田中一喜氏、本社=名古屋市中区)の株式の一部を9月16日付で取得したことを発表。AIを活用した高精度な3次元地図作成技術や環境認識ソリューションを提供する同社との連携強化により、自動運転分野での技術開発、事業展開を加速させていく方針が説明された。
歴代会長3名をパネリストに招き
『名機工同友会の歴史を振り返る』
名機工同友会 10月例会でパネルディスカッション
名機工同友会(会長=嶋﨑晴久氏・シマザキ商会社長)は10月14日、名古屋市中区の東京第一ホテル錦にて10月例会を開催。正会員ら21名が参加した。この日は、名機工同友会第8代会長の田中知之氏(ミユキ商会)、同じく第9代会長で現在同会顧問の鈴木俊雄氏(マルマン商事)、同じく第10代会長で現在同会顧問の吉野栄一氏(吉野機械工具)の3名をパネリストに招き『名機工同友会の歴史を振り返る』と題したパネルディスカッションを開催した。
開会を前に嶋﨑会長が「今まで名機工同友会の歴史を振り返るという例会は無かったように記憶しています。あくまで私個人の意見ですが、名機工同友会は中部地区の業界内では最強の任意団体だと思っております。そんな立派な歴史を作ってこられた歴代会長から、今の名機工同友会に対する助言等々も含め、お話をお伺いできればと思っております」と挨拶。パネルディスカッションでは、歴代会長3名が名機工同友会へ入会することとなったきっかけ、名機工同友会で今なお記憶に残っている事業や人物などについて懐かしくも楽しく語っていた。
名機工同友会は、今から62年前の1963(昭和38)年に「名古屋機械工具経営同友会」という名称で、正会員22社が集まり発足。1998(平成10)年に現在の「名機工同友会」へと名称を変更し、現在に至る。
社名を「日本酸素」に変更
大陽日酸 2026年4月から
大陽日酸(社長=永田研二氏、本社=東京都品川区)は、社名を現在の「大陽日酸」から「日本酸素」へ2026年4月1日に変更すると発表した。
同社では来年4月から、2030年のあるべき姿を目指して、新たな中期経営計画がスタートする。創業120年となる2030年に向け、さらに産業ガス事業を進化させていく意志を新社名に込めた。
同社は1910年の創業以来、日本の産業ガス業界におけるトップランナーとして、産業ガスの普遍性と拡張性を軸に、主力製品や事業構造を変化させながら成長してきた。事業のグローバル化に伴い、2020年には純粋持株会社によるグループ運営体制に移行し、日本酸素ホールディングスが発足。同社は主に日本国内を中心とした事業会社となったが、グローバル展開の源流として、産業ガスの原点「酸素」に立ち返り、親会社の日本酸素ホールディングスと名称を統一する。
社名変更に伴い、グループ会社のうち社名に大陽日酸を冠する各社においても社名変更の手続きを進めていくとしている。
同社30か所目の物流センター
「プラネット新潟」上棟式
トラスコ中山 2026年8月稼働予定
機械工具卸売商社のトラスコ中山(社長=中山哲也氏、本社=東京都港区)は10月10日、新潟県三条市で建設中の物流センター「プラネット新潟」の上棟式を執り行った。
同社は全国28か所の物流センターに約61万アイテムの在庫を保有し、顧客の工場用副資材調達の利便性向上に努めている。2026年8月稼働予定の「プラネット新潟」は、同年5月に稼働予定の「プラネット愛知」に次ぐ30か所目の物流センターとなり、在庫保管能力と出荷能力の向上により更なる即納体制の強化を図る。
新潟県三条市にある既存の同社ホームセンタールート向け物流センター「HC東日本物流センター」は、建設から約30年が経過し建物や設備の老朽化が進んでいる。また、ホームセンターへの売上拡大に伴い、在庫保管能力や出荷能力が限界に達しつつあることから、より効率的な作業環境を構築するとともに、ホームセンターをはじめ、より多くの顧客ニーズに応えるため「プラネット新潟」の建設を決定した。
「プラネット新潟」の主な役割は、(1)ホームセンタールート向け納品体制の強化(2)ファクトリールート向け大物商品出荷センター(3)海外メーカー商品のストックセンター(4)新潟支店向けの在庫確保。現在、HC東日本物流センターに併設している新潟支店も「プラネット新潟」の新設に合わせ移転する。
最先端の物流機器を導入した同社最大の物流センター「プラネット埼玉」(埼玉県幸手市)には61万以上の在庫アイテムがあるが、今後も在庫商品を拡大していくにあたり、出荷頻度を加味しつつ「プラネット埼玉」では高速自動梱包出荷ライン(I-Pack¥文字(U+00AE))に投入できるサイズの商品を在庫し、「プラネット新潟」ではそれ以外の大物商品を保管・出荷することで、東日本全体で約80万アイテムの即納体制を整えていくという。
上棟式には、設計を担当する日建設計の佐藤健常務執行役員、施工を担当する鹿島建設の木村淳二執行役員らとともに中山社長が出席し、上棟の儀や玉串奉奠などの儀式が滞りなく行われた。
【プラネット新潟の概要】所在地=新潟県三条市福島新田字松橋下丁431番2▽アクセス=上越新幹線「燕三条」駅より7¥文字(G0-8426)(車で15分)▽敷地面積=7956坪(2万6300¥文字(G0-8429))▽延床面積=1万4622坪(4万8338¥文字(G0-8429))※東京ドーム約1個分▽建物構造=複合構造(柱RC梁S構造)、免震構造、消雪装置▽階数=倉庫4階、事務所3階▽能力=保管点数16万アイテム、出荷行数=3・5万行/日▽建屋竣工=2026年3月末(予定)▽出荷開始=ホームセンタールート向け2026年8月(予定)、ファクトリールート向け2026年10月(予定)▽投資総額=土地・建物約168億円、設備約14億円。
鈴木建吾氏(八幡ねじ代表取締役会長)
「お別れの会」しめやかに
全国から1000人以上が参列
7月14日に78歳で逝去した八幡ねじ代表取締役会長鈴木建吾氏のお別れの会が10月10日、名古屋市中区の名古屋観光ホテル那古の間において開かれた。3部制で行われ、全国から取引先や業界関係者など1000人以上が参列。祭壇の遺影に献花し、故人との別れを惜しんだ。
鈴木建吾氏は、横浜国立大学経済学部卒業後、富士通に勤務し、昭和46年八幡ねじに入社。同62年に創業者鈴木利則氏よりバトンを受け取り、代表取締役社長に就任し「三方善」を社是とした。
平成30年まで31年間社長を、同年71歳から代表取締役会長として生涯現役で務め上げた。入社から54年間、社業発展のかなめ「整流化」を実現するために、努力と挑戦を重ねた。八幡ねじは、その道を歩み「整流化」を拓いてきた。
一方、鋲螺業界の発展にも尽力し、愛知鋲螺商協同組合理事長、日本ねじ商業協同組合連合会会長を歴任。また、名古屋東ロータリークラブ会長として社会奉仕にも力を注いだ。
令和元年春の叙勲で「旭日双光章」を受章。同3年には母校の横浜国立大学に「八幡ねじ・鈴木建吾奨学金」を設立した。
受賞関係では、中部産業連盟『VM推進賞』(平成9年)、『2002年度グッドデザイン賞・日本商工会議所会頭賞』(同14年)、『デザイン・エクセレント・カンパニー賞』(同17年)、経済産業省『中小企業IT経営力大賞・経済産業大臣賞』(同20年)、『2013年度グッドデザイン賞』(同25年)、『2021年日本パッケージデザイン賞・銀賞』(令和2年)ほか多数受賞。
会場には同氏の功績を記した年表と当時の写真、多数の賞状などが動画とともに展示され、参列者は在りし日の姿をしのんだ。
「CoroMill?MS20」を拡充
サンドビック・コロマント
鋼加工用チップ、防振
機構付き円筒シャンクホルダを発売
サンドビック・コロマントは、10月1日より「CoroMill¥文字(U+00AE)MS20」の新製品として鋼加工用チップ及び防振機構付き円筒シャンクホルダの販売を開始した。
「CoroMill?MS20」は肩削り、正面フライス、溝加工、ランピング、プランジ加工など幅広いフライス加工に対応する高汎用性フライスカッター。革新的デザインコンセプトと製造技術により、多様な切込み量やアップ/ダウンミリングに関わらず、これまで以上の高い壁面精度と長い工具寿命を達成する。肩削り加工において、高い加工安全性でユーザーの生産性向上とコストダウンを実現する。
今回新たに鋼(ISO-P)用チップがラインナップに加わり、従来のステンレス鋼(ISO M)および耐熱合金(ISO S)加工向けに加えて、加工領域が拡大した。チップは最適化されたブレーカを備えた片面2コーナ仕様で、優れたパフォーマンスと長寿命を両立。厚みを厚く一定に保つことで欠けを防止し、軸方向の切込み量に左右されない安定した性能を発揮する。
さらに、新たに導入された防振機構付き円筒シャンクホルダは、先端部に軽量なスチール材を使用し、シャンク側は高剛性なカーバイド材で補強されている。これにより質量が後方に集中し、回転軸に対して安定した慣性モーメントが生まれ、振動の抑制効果がさらに高まる。加えて、先端に内蔵された制振機構との相乗効果により、加工時の安定性が向上し、工具寿命や加工精度のさらなる向上が期待できる。
ラインナップは、カッター径φ16~φ84㎜、シャンクはアーバ取付、円筒シャンク、Coromant Capto、EHカップリング、ねじ式カップリング、防振タイプ円筒シャンクの6種類。チップはノーズR0・2㎜~3・1㎜まで、鋼(ISO-P)用37品目、ステンレス鋼(ISO M)および耐熱合金(ISO S)用49品目を展開している。
ヒューマノイドロボット専用施設開設へ
フィジカルデータ生成センター構築プロジェクト参画
山善 社会実装を加速させる
ものづくり商社のリーディングカンパニーである山善(社長=岸田貢司氏、本社=大阪市西区)は、ヒューマノイド(人間に似せた形状の)ロボット向けに最適化された「ヒューマノイド・フィジカルデータ生成センター」の構築プロジェクトに参画すると発表した。本プロジェクトは同社が2025年4月より業務提携しているINSOL-HIGH(社長=磯部宗克氏、本社=東京都千代田区)が主催するコンソーシアム型の取り組みだ。今後はヒューマノイドロボットの社会実装を加速させるため、製造・物流・ロボティクス分野の先進企業に対して本プロジェクトへの参加を呼びかけ、業界を横断した連携体制で推進していく。
ヒューマノイドロボットが自律的に作業を行うには「どのように動けばよいか」を学ぶための「学習データ」を大量かつ高品質に蓄積することが不可欠である。そのため、多くのロボットでさまざまな動きを記録し、集めたデータを分かりやすく整理・分類する仕組みも必要となる。本プロジェクトでは、海外メーカーのヒューマノイドロボットを最大50台稼働させる大規模なフィジカルデータ生成センターを2026年春頃に構築する予定で、現在は、年内に10社の参画を目指し、各業界の大手企業と交渉をおこなっている段階だという。
まずは、参画企業各社がヒューマノイドロボットを複数台活用し、動作データの収集やデータ化のノウハウを習得するとともに、ピッキング、組立、検査、搬送といった作業を自動化するための学習モデルを構築。続いて各社が取得したデータを活用しあうための共有データ基盤を構築する。「実作業の動きに基づいた貴重なデータ」として体系化し、INSOL-HIGH社が構築するデータプラットフォームに集約することで、高品質で汎用的な学習データを蓄積できる。これにより、人の作業を幅広く再現可能にすることを目指すという。最終的には、各社が自社固有の現場ノウハウや秘匿性の高い業務に対応するために最適なデータを生成し、独自の自動化モデルを開発することで、コストを削減しつつ現場で学習させながら、さらなる作業成功率の向上を実現できる。
山善専任役員の中山勝人トータル・ファクトリー・ソリューション支社長は「このプロジェクトはヒューマノイドロボットが〝社会の一員〟として共に働くための重要な第一歩です。私自身、中国でフィジカルデータ生成センターを目の当たりにし、その重要性を実感しています。ただ、中国と同じことをするのではなく、日本の強みや独自性を発揮するためには、〝データの共有化〟がポイントになると考えています。今回のプロジェクトを通じ、先進企業各社さまとの協力により、いち早く社会実装を実現することはもちろん、日本から世界に向けて新しいビジネスチャンスの創出を目指します」とコメントを発表している。
技能五輪国際大会日本代表選考会
DMG森精機伊賀事業所で開催
会場とCNC旋盤等を提供
DMG森精機(社長=森雅彦氏、グローバル本社=東京都江東区)伊賀事業所で9月30日~10月2日の3日間、第48回技能五輪国際大会における「CNC旋盤」および「CNCフライス盤」2職種の日本代表選手選考会が開催された。
技能五輪国際大会は参加各国における職業訓練の振興と青年技能者の国際交流、親善を図ること(中央職業能力開発協会Webサイトより引用)を目的に、原則2年に一度開催されている。同社は、かねてより若手人材育成および製造業全体の技術力底上げに取り組んでおり、技能五輪国際大会には第39回静岡大会以降、競技で使用する機械の貸出提供を通して継続的に支援している。
本選考会は、2026年9月に中国・上海で開催される第48回技能五輪国際大会に向けて、日本代表選手を選出することを目的として実施。選手は与えられた図面に基づき制限時間内に加工を完了させる必要があり、高いスキルと強い精神力が求められる。当日は、全国から選抜された7名の選手が最新鋭の工作機械を用いて高度な技能を競い合い、日頃の研鑽の成果を発揮していた。
DMG森精機は、同社の基幹機種であるNLX2500¥文字(U+2013)7002nd Generation(旋盤)2台、NVX5100¥文字(U+2013)402nd Generation(立形マシニングセンタ)2台、計4台を提供し、前回大会の選考会に引き続き同社伊賀事業所内にて競技が開催できるよう会場提供に協力した。また、本選考会来場者向けに同社の伊賀グローバルソリューションセンタ内を案内する見学ツアーを3日間実施。最新の5軸加工機やアディティブ・マニュファクチャリング機をはじめ、MX(マシニング・トランスフォーメーション)について紹介した。さらに、ドイツにおいても同様に、2025年9月に開催された「EMOハノーバー2025」にて、「CNC旋盤」職種のドイツ代表選手選考会が行われ、同社は機械提供と技術支援を実施している。
2028年には第49回技能五輪国際大会が愛知県で開催されることが決定。日本での開催は1970年の東京、1985年の大阪、2007年の静岡に続き21年ぶり4回目となる(厚生労働省発表)。DMG森精機は今後も本大会および本選考会への支援を通じて、将来の製造業を担う人材育成のための取り組みを行っていく。
「MISUMIfloow」
2025年度グッドデザイン賞受賞
ミスミグループ 間接材調達の業務時間を約7割削減
ミスミグループ(社長=大野龍隆氏、本社=東京都千代田区)が提供する間接材トータルコストダウンサービス「MISUMI floow(フロー)」が2025年10月15日、日本デザイン振興会が主催する「2025年度グッドデザイン賞」を受賞した。この賞は日本唯一の総合的なデザイン評価制度で、1957年の創設以来、製品や建築、サービスなど多様な対象を通じて、デザインのチカラで暮らしや社会をより良くすることを目指している。カタチの有無を問わず、人の理想や目的を実現するために築かれた仕組みや活動もデザインと捉え、その質を評価・顕彰する点が特徴だ。
「MISUMI floow」は、デジタル技術革新により顧客の需要データを起点に、工場における間接材調達の整流化を実現するためのトータルコストダウンサービスとして誕生した。利用頻度に応じた最適チャネル設計により、発注・納入・棚卸といった作業を不要とし、間接材調達の業務時間を約7割削減する仕組みが今回の受賞選考で高く評価されたようだ。
前述の通り、属人的で非効率な工場の間接材調達に対して、「MISUMI floow」が利用頻度別に最適チャネルを設計することで、発注や納入、棚卸といった作業は不要となり、間接材調達における業務時間を約7割も削減する仕組みを実現することが可能となった。発注・納品・棚卸を一括で担い、需要データを起点に自販機やECを組み合わせることで「納期ゼロ時間」に近い体験を提供してくれるという。これにより、現場は本質的な業務に集中できモノづくりを推進できる環境が整う。さらに、利用データの蓄積による在庫最適化、人的ミス防止、サプライチェーン全体での過剰梱包削減といった環境貢献も望める。確実短納期のサプライチェーン基盤とDXの掛け合わせにより、工場の生産性・持続性・働き手のウェルビーイングを高めるデザインであり、すでに中国や日本では実績を上げているようだ。
「グッドデザイン賞」は、1957年に旧通商産業省によって設立された「グッドデザイン商品選定制度」(通称Gマーク制度)を継承する、日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の運動である。単にモノの美しさを競うのではなく、産業の発展と暮らしの質を高めるデザインを、身の回りのさまざまな分野から見いだし、広く伝えることを目的としている。世界でも有数の規模と実績を誇るデザイン賞として国内外の多くの企業やデザイナーが参加すると共に、良いデザインを社会に広める運動としても多くの人びとから支持されている。
「MISUMI floow」は、デジタル技術革新により顧客の需要データに基づいた最適なチャネルでの商品提供を可能とし、工場における間接材調達の整流化を実現するトータルコストダウンサービスである。調達担当者の発注の手間を省き、在庫量を可視化することで調達時間を約7割も削減でき常に適切な在庫管理を実現。利用者が高頻度で使用する消耗品は、工場常設の自販機までミスミが納品を行ってくれる。このシステムは、いわば製造現場における〝富山の置き薬”のシステムに近いものがある。自販機内の在庫はミスミ資産となるので過剰在庫を抱える不安はない。さらに、自販機から取り出す際は顔認証やIDパスが必要になるため使い過ぎを防ぎ、社員のコストに対する意識改革にもつなげられる。
「山田貞夫音楽賞」4名受賞
特選受賞は松村詩史さん
山田貞夫音楽財団 第7回指揮者オーディション
公益財団法人山田貞夫音楽財団(代表理事=田中真紀代氏、所在地=名古屋市中村区・ダイドー内)主催の「第7回指揮者オーディション」最終選考会が10月9日、名古屋市青少年文化センター・アートピアホールで行われ、若手指揮者の松村詩史さん(特選)、佐藤秀義さん、園山正洋さん、小林剣心さん(2年連続)が山田貞夫音楽賞を受賞した。特選の松村さんは、12月1日に同ホールで開催される「第7回新進指揮者コンサート」で指揮を披露する。演奏はセントラル愛知交響楽団。
このオーディションは、愛知県内で演奏経験のある指揮者の活動を支援し、愛知県の文化芸術の振興に寄与することを目的に同財団が実施するもの。愛知県で指揮者として演奏実績のある38歳以下の人を対象とし、受賞者には賞金が贈呈される。
今回のオーディションには14人の応募があり、書類審査(第一次選考)を経て9人の指揮者が第二次選考に進出。最終選考会前日に同会場で行われた第二次選考では、課題曲ベートーヴェン「エグモント」序曲の指揮に臨み、5人が最終選考に残った。
最終選考会では各自選択曲を指揮し、審査の結果、4人の山田貞夫音楽賞受賞が確定。このうち、ベートーヴェンの交響曲第5番「運命」を指揮した松村さんが特選を受賞した。また、佐藤さんには山田弘子評議員より特別賞が贈られた。
選考委員は、瀬戸和夫氏(愛知芸術文化協会理事)、川田健太郎氏(名古屋芸術大学准教授)、寺田史人氏(寺田弦楽四重奏団、プシャーテルアンサンブル主宰)ほか、演奏家3人の合計6人が務めた。
冒頭の挨拶で田中代表理事は「昨日、第二次選考が行われ、9人それぞれの個性あふれるエグモントは今でもまだ余韻が残るくらい迫力がありました。このような大掛かりな指揮者オーディションができることを主催者として大変嬉しく思う次第です。当財団も10年以上になり、財団に関わった方々のご活躍を聞くことも多くなりました。指揮者部門の方々のご活躍も応援しています」と述べた。
また、最後に財団創設者の山田貞夫会長(ダイドー会長)が受賞者への祝辞で「戦争は良くありませんが、音楽や文学で競い合うのは良いことです。人生を豊かなものにしていくよう頑張ってください」と述べるとともに関係各位に引き続き財団への協力をお願いし、オーディションを終了した。
松吉正訓氏(ジーネット)が優勝
岐阜機工会 第11回親睦ゴルフコンペ
岐阜機工会(会長=田口健一氏・タグチ社長)は10月8日、「第11回親睦ゴルフコンペ」をやまがたゴルフ倶楽部・美山コース(岐阜県山県市)で開催した。
当日は7組26人が参加し、OUT・IN同時9時スタート。天候にも恵まれ、笑い声の絶えない楽しいコンペとなった。
優勝は松吉正訓氏(ジーネット)G83/H13・2/N69・8。
2位が安藤義和氏(安藤)G78/H6・0/N72・0。
3位が田口浩治氏(MOLDINO)G106/H31・2/N74・8。
※ダブルペリア方式